MOT在学生とのトークセッションの録画をUP!ーPart 4ー



<「実践CXO・起業家ケーススタディ」とは>
東京理科大学大学院経営学研究科技術経営専攻(MOT)の「実践CXO・起業家ケーススタディ」はMOT目玉講義の一つです。前期と後期に実施しています。
シラバスでは「将来の経営者CEO、CTO、専門性の高いCXO人材を目指す学生が、実務に携わっている経営者、CTO、起業家などイノベーションや経営の実践者から、講演を聞き、質疑応答を行い、その後、教員と学生でグループディスカッションも含めて行う授業です。
イノベーションや経営のケーススタディを、その当事者と議論することで、コア科目等で獲得した知識を確認し、それを実践知、考え実行できる能力として定着させることを目的とする」としています。
後期の授業の最初のゲストは、日立化成株式会社の社長を7年間務められ、現在、昭和電工マテリアルズ名誉相談役の田中一行氏です。
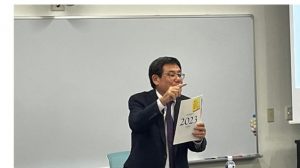
<田中一行氏の御講義の概要>
『日立化成 7年間の経営の省察』と題する御講義では、キャリアヒストリーに続いて、7 年間の経営の概要をお話し頂きました。その後、事業、組織、人の変革についてご説明されました。ポイントだけ、少しご紹介します。
◎事業の変革
半導体実装に関する総合的なソリューションを提供するコンソーシアム「JOINT( ジョイント) 」設立の経緯を御説明して頂きました。
社長在任中の2014年、オープンイノベーションを目的として、日立化成内にパッケージング・ソリューション・センタを立ち上げ、半導体実装に関するソリューション提案を開始されたとのこと。その後、2018年には、多くの装置メーカー、材料メーカーを加え、総合的なソリューションを提供するコンソーシアムの設立へと成長したとのお話でした。
「JOINT」については、昭和電工のホームページに最新の情報が記載されています。
◎組織の変革
2011年から「対話と挑戦の文化 」を醸成する準備を始め、執行役全員が、グループの「過去」、「現在」、「未来」について議論し、経営層としての想いを表現しました。
表現に「マネジメントメッセージ」と「コミュニケーションアート」の両方のメディアを活用されました。
特に、後者のアート(絵)が経営者の想いを伝え、従業員に共感を広げる力に驚嘆しました。
経営にアートを活用した積極的な実例ですね。

◎人の改革
「省察」という言葉を大切にされているのが印象的でした。
今回の御講義のタイトルにも含まれています。反省だと悪い部分だけの振り返りとなりますが、省察は良い部分も確認しつつ、悪い部分も振り返るという幅広い視点だそうです。
「省察」した後の「気づき」の際に、「コーチング」という個々人の能力を引き出し、実践力を強化する手法を適用すると部下の成長を促せるそうです。
田中氏はコーチングの資格を取得されていることにも驚きました。

