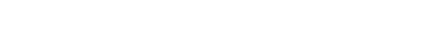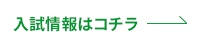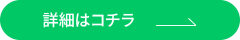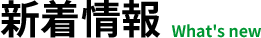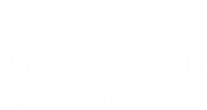2025.06.26 修了生が紹介するMOTの講義
専門科目「科学技術・産業政策」(井上悟志教授)│第5回:R&D政策を構成する諸制度
【2025年度春学期】

井上悟志先生がご担当の「科学技術・産業政策」を受講した。井上先生は通商産業省(現在の経済産業省)に入省されたのち、宇宙、エネルギー、IT、農林水産業など幅広い分野で科学技術・産業政策にたずさわり、海外での勤務もご経験されている。「科学技術・産業政策」はイノベーションを起こす国家政策の概要や歴史と国際⽐較、経産省ハイテク政策や⼀般の産業政策、その中での競争法の動向、最近の国家安全保障との関係について学び、それを⺠間がどのように活⽤するかを理解することを目的としている。
私が受講したのは全8回の授業のうち第5回で、TLOや日本版バイ・ドール条項、専門職大学院での社会人教育、産学官連携による共同研究強化などR&D政策を構成する諸制度について講義をしていただいた。国や自治体が税金を投入する政策においては、その効果が計測され開示されることで政策の妥当性を評価する必要がある。1980年に米国でバイ・ドール法が成立した背景には、連邦政府が巨額の資金を投じた研究成果のわずか4%しかライセンス供与・実用化されなかったことがある。税金で開発された知財が企業を通じて実用化され産学連携による産業振興が活性化されることを目的に、研究実施機関への知財の所属やライセンス供与を認めたこの政策は、知財の死蔵を抑制し研究成果の実用化を促す一定の効果があった反面、行き過ぎた大学側の学術研究の商業化により本来の目的とは逆に産学連携が停滞する事態を引き起こした点は、政策の運用段階の難しさを感じる。
また、日本と米国の制度や意識の違いをめぐる指摘も興味深かった。国立大学が法人化されるまでは政府の一機関の位置付けであったことなどから、日本では研究成果は公的なものであるとの意識が根強く、知財の商業利用に積極的な米国と比べ社会インパクトにふさわしい研究の対価を得られていないなど、日米双方における産学官連携の実情をよく知る井上先生の解説は実に興味深いものであった。
産学官連携によるイノベーション促進を目的とした「イノベーション促進産学官対話会議」においては、経団連の提言を受けて平成28年に文科省・経産省主導で産学官連携による共同研究強化のための2つのガイドラインが作成された。費用負担や知財マネジメントについて産学が共通のベースを持つことは、様々な立場で共同研究に関わるステークホルダーの取引コストを低減するうえで有効である。また今回の講義を通じて、大学と企業の一対一の共同研究11類型とコンソーシアム型5類型のモデル契約書をまとめた「さくらツール」や、産学双方で常勤職員としての身分を持つことが可能な「クロスアポイントメント制度」など、産学の共同研究をスムーズに進めるための制度を知ることができた。
これらの情報を事前に持っているかどうかで大学との共同研究の進め方は大きく異なるだろう。当社においても大学との共同研究は毎年複数実施しており、今回得られた知識はこれらの業務をスムーズに進めるうえで価値のあるものだと考える。アカデミックな知識を増やすだけではなく、今ある課題にすぐ活用できる専門知識を学ぶことができる専門職大学院のメリットを感じた講義であった。
執筆:2021年度修了生(建設業勤務)