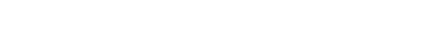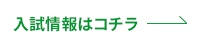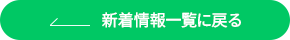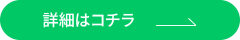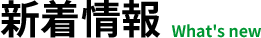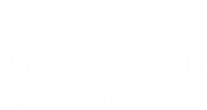2025.11.09 修了生が紹介するMOTの講義
基盤科目「アカウンティング」(岡田将稔教授)|第6回:経営戦略と管理会計 ~バランストスコアカード(BSC)とケース研究~
【2025年秋学期】

「アカウンティング」というと簿記や仕訳のような会計の基礎を思い浮かべるかもしれないが、理科大MOTの講義はマネジメントの立場で財務会計や管理会計を活用することを目的に、より実践的な内容を扱う点が特徴だ。本科目は、三菱UFJ銀行と兼職で教壇に立つ岡田将稔教授(※1)、公認会計士で自らも会社を経営する小林憲司講師(※2)が担当。現役で実務に携わる教員により、教科書的な会計の知識や理論にとどまらず、企業の情報開示には決して出てこない失敗や試行錯誤の事例を通じた議論が展開されている。
今回受講の機会をいただいた第6回は管理会計を担当する岡田教授により、経営戦略の策定や実践に役立つ管理会計の知識と応用の考え方、そのツールとして「バランストスコアカード(BSC)」が解説された。BSCは財務指標に加え非財務指標を用いる包括的な業績測定・評価システムだが、実際に導入した企業や現場からは「うまくいかなかった」という声が聞かれることも多い。自身もビジネススクールだけでなく博士課程で研究を続けた岡田教授は、最新の論文にも触れながら「BSCはあくまでも手段であり、使い方が問題」と強調する。ある企業では業績指標をまとめた冊子が立つほどになったという事例にも触れながら、管理職も多い受講生に「ミドルマネジメントの役割はいかに無駄な指標を止めるかにある」と語る。
こうしたBSCの活用や管理会計の実践によるマネジメント・コントロールは、戦略に適合する組織を構築するためにも重要だ。一方で、企業内部の取り組みで公開情報が乏しいことから「ナマのケース不足」のため、ビジネススクールでは深掘りしづらいテーマでもある。岡田教授での講義は実務家としての経験や、専門であるファミリービジネス研究での知見により、教科書では知ることができない生々しい情報が豊富に提供される。こうしたケースからの示唆は、教授自身もかつてビジネススクールで違和感を持ったという全社の経営戦略と現場での日々のPDCAサイクルの乖離の原因を明らかにして、理論やツールと実践を結びつけるのを助けてくれる。残念ながらここでは紹介できない多くの「スライド投影のみ」の資料により、理解を深めることができるのはこの講義の魅力のひとつだ。

講義の後半ではより詳細な事例研究として、岡田教授とともに三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)でウェルスマネジメント(WM)に携わるゲスト講師により、WM事業の立ち上げについてお話を伺うことができた。WMは個人や家族の資産を総合的に管理・運用する富裕層向けサービスで、総合金融グループとして銀行・信託・証券の各業態などの経営資源を持つMUFGの強みを活かした事業だが、横断的なサービス提供にはそれぞれの競争優位の源泉や成功体験が組織変革の阻害要因にもなったという。ゲスト講師からは時に内部資料も織り交ぜながら、WMの事業戦略を実現する組織変革を行うにあたり、BSCの活用やマネジメント・コントロールの実践が語られた。当事者にしか語れないエピソードばかりであり、今やグループ内で模倣されるまでになったという成功に至るまでの工夫や試行錯誤、苦難の述懐は受講生にも共感やヒントになるものが多くあったと思われる。
ゲスト講師による事例研究以外にも、岡田教授の講義では多様な業種や組織レベルの成功・失敗事例のほか、自身が経験した不条理な施策について突っ込みを入れながらの紹介もあり、様々なバックグラウンドを持つ学生が共感と納得をしながら自分の職場について考えることのできる内容となっている。組織のあり方をアニメ「鬼滅の刃」にたとえたり、政治経済の時事ネタも盛り込まれたりと教室に笑いが起こる場面もたびたびあった。MOTでは公開授業(※3)もたびたび開催しているので、興味のある方はぜひ一度実際の講義を体験していただければと思う。
執筆:2022年度修了生(損害保険業勤務)
※1 岡田将稔教授:https://most.tus.ac.jp/facuity/masatoshiokada/
※2 小林憲司講師:https://most.tus.ac.jp/facuity/kenjikobayashi/
※3 MOT公開授業:https://most.tus.ac.jp/topics/introalumnimotlectures/1560/