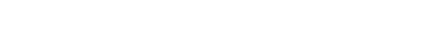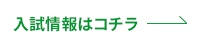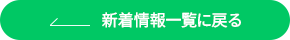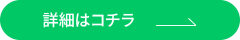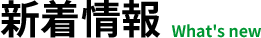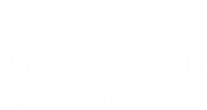2025.10.24 修了生が紹介するMOTの講義
専門科目「デザイン・コンセプト創造」(中山裕香子教授)|第3回:情報収集に関するケーススタディ(1) ~グループディスカッションが生む新たな発見~
【2025年度秋学期】

理科大MOTは「イノベーション」を中心テーマとしており、学生はそれぞれが新たな商品・サービスや生産方式、ビジネスモデルやマネジメントの実現に取り組んでいる。このような世の中にまだない提案を実践するにあたって、重要になるのが軸となる「コンセプト」の存在だ。「デザイン・コンセプト創造」の講義は、情報収集からプロトタイピング、開発、事業化といった各プロセスにおいて、論理思考では捉えきれない暗黙知の問題解決にアプローチするデザインやアートの思考も取り入れながら、自らコンセプトを創造する考え方とスキルを習得することが狙いだ。
コンセプトは、それぞれのビジネスやテーマのために考案された特殊解でなければならないという難しさがある。そこでコンセプトの創造を学ぶ本科目では、知識を学ぶことに加えてケーススタディによる協働の実践が特長となっている。今回受講の機会をいただいた講義では、まずコンセプトを考えるための前提となる知識や思考法とともに、ヤマハの電子楽器「TENORI-ON」(テノリオン)や米アップルのiPhoneといった数々の具体例が紹介された。野村総合研究所で多様な業界の戦略立案や調査研究に携わってこられた中山裕香子教授(※1)ならではの、幅広く身近な事例や話題を通じて、デザインやアートという抽象的な思考の理解が促されたように思う。
ケーススタディ(ケースメソッド)では、バーコードやRFIDなどの自動認識技術・ソリューションを手掛けるサトーの事例が取り上げられた。同社は長年にわたって、「全社員が毎日、3行で社長に提案・報告する」という「三行提報」の制度を採用し、経営トップの情報収集と社員からの提案に役立てている。文字数にして127文字以内という三行提報が始まったのは1983年からであり、140文字の投稿ができるツイッター(現X)の2006年より早いという点でも興味を引くケースだ。今回は対面・リモート別に7チームに分けられ、ケースが成功した鍵やさらなる発展のアイデア、自社が学ぶべきポイントなど、各グループで目的・ゴールを設定して1時間にわたり議論の時間が設けられた。
発表は各グループからの報告4分、質疑3分という限られた時間ではあるが、受講者からは積極的な意見が寄せられ、講義の予定時間を超過して議論は白熱した。今回のケースについて事前配布された資料は35ページもあるだけに、報告や質疑では社長の経営判断のようなメインの話題からエピソード的な出来事まで、多岐に及ぶ視点から発言がなされた。コアとなるメッセージを読み取るだけでなく、サイドストーリーから学ぶことができることもケーススタディの面白さということがわかる。

ケーススタディは現実に世の中で起きていることを取り上げるだけに、必ずしもスッキリする内容ばかりではない。だからこそグループワークの目的は正しい答えをみつけることではなく、自分はどこが重要だと思うのか意見を交わして互いに新たな発見を得ることだという。こうしたケーススタディの訓練はコンセプトを生み出すだけでなく、それぞれの所属組織でデザインやアートの思考による価値創造を実践するのにも役に立つだろう。「同じケースでも見るところ、感じるところ、アウトプットが異なることがグループディスカッションの醍醐味」と中山教授がまとめたように、メンバーそれぞれの意見から新たな発見を得ることができる「協働」の威力と魅力が大いに感じられる講義であった。
執筆:2022年度修了生(損害保険業勤務)