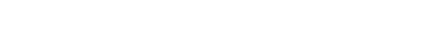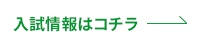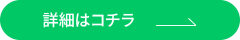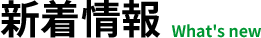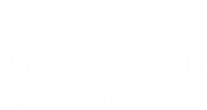専門分野の深い理解を目指し、
実践的な研究やディスカッションを通じて学んでいく。
各ゼミの紹介
▼青木ゼミ
担当教授:青木 英彦
私のゼミ指導方針は、大きく 3 つあります。
第一は、自分が業務を通じて得た自分ならではの問題意識にこだわるということです。自分の問題意識を高め、徹底的に追究し、研究テーマを設定します。
第二は、一次情報を重視することです。論文を調べるときには世界中の原文にあたる。人の意見を求めるときには、実際にその人のもとに出向いて話を聞く。そうして現場・現物・現実に当たることが、研究のオリジナリティにつながります。実際、2024 年 3 月にゼミ合宿として福岡県宮若市にある AI 研究開発拠点を訪問し、担当者の方々とディスカッションをしてきました。現場・現物・現実を前にして、情報のインプットが変われば、おのずとアウトプットも変わってくるものです。
そして第三は、経営者目線を意識することです。仮に今、経営職に就いていなくとも、「自分が経営者であればどうするか」「企業経営はどうあるべきか」などと自問することを求めます。マネジメントは見よう見まねで行いがちですが、そこにはしっかりとしたセオリーが存在します。理論講義、ケーススタディ、グループディスカッション、グループ発表、ゲスト講義などと組み合わせながら、理論と実践、抽象と具体を行き来することで、使えるセオリーを身につけていく『結果を出せる教育』を多面的に提供しています。
▼井上ゼミ
担当教授:井上 悟志
井上ゼミでは、議論を重視しています。学生同士、学生と教員との間で、ただひたすら議論をします。最初は、「問い」を固めるための議論を行います。なぜ東京理科大学 MOTへ入学したのか。何が悩みなのか。何を学ぶのか。それはなぜなのか。結局、自分は何なのか。議論を通じて、修了までぶれることのない確固とした「問い」を可視化します。次に、相互理解のための議論を行います。自分の言葉は相手に伝わっているだろうか。業界や社内の論理を当たり前のことのように振り回していないか。相手が理解できていないという事実を繊細に感じ取れているか。理解に限界があるということを前提として互いの「問い」に寄り添い合えるか。ここまで来て、ようやく議論が噛み合うようになります。その後は、利他の精神を持って励まし合い、支え合いながらグラデュエーションペーパーを一歩一歩完成させていくことになります。多くの時間は、自分ではない誰かの「問い」の答えを見つけるための議論に費やされることになります。ゼミの時間を勉強に使うのはもったいない。ここにしかない学びを追究していきます。
▼内海ゼミ
担当教授:内海 京久
本ゼミの到達目標はGraduation Paper執筆を通した「本質を考える力の獲得」である。その目指す姿は、「MOT入学のきっかけとなった問題意識を解決すべき課題として顕在化させること」「その本質的な原因・メカニズムを明らかにすること」「現実的な抜本的解決策を提案すること」である。これらが修了後の実践において非常に強力な武器となることを、本学修了生の私はかつて実感したし、ゼミ生にも是非習得してほしいと考えている。そのために以下をゼミで実践する。
まず、問題意識を「なぜ~なのか」という問いとして設定する。正しい問いの設定は正しい回答に勝る。しかしながら、多くのMOT入学者にとって問題意識は潜在的であり言語化が難しい状態である。このため、ゼミでは各自の実務における「シンボリックな事実」の発見から、「不思議」と思える問いを抽出し、その「真の原因」の仮説構築と実証を経て、「解決策の提案」をブラッシュアップする。
次に、問題に対する本質的な原因やメカニズムを明らかにする力を養う。大切なのは、「問題から解決策へ飛ばない」ことである。原因がわかれば抜本的な解決策は自ずと導かれる。このScienceで当たり前の考え方を技術経営の実務家は驚くほど実践できていない。なぜなら、経営や商品化、研究開発プロセスのような社会科学的現象の原因究明は、実験検証ができないためつかみどころがなく、そのスキル習得が難しいからである。ゼミではそのスキル習得を目指し、各自の問題意識に対する本質原因の仮説を、なぜとその答えの繰り返しや事実データとの行き来によってとことん深く考察し、論理を精緻化するプロセスを経験してもらう。
▼岸本ゼミ
担当教授:岸本 太一
実務で直面する課題の解消には、大きな課題になるほどテーマや分野に限らず、企業や所属部門の中だけではなく、上や外にいる様々なプレイヤーも巻き込んだ長期計画や戦略が必須です。しかし、そうした広く高い視野に基づいた大型の計画や戦略を、日々の業務の中で構想することは困難です。裏を返せば、目先の業務の対処に追われずに「じっくり時間をかけられる」点に、ビジネススクールで社会人が研究する利点が存在します。
多忙な実務家は「解決策先ありき」になりがちです。しかし、解決策の考案に入る前に、まずは自身が解消を試みたい課題の原因と構造を、視野を高めかつ拡げる形で徹底的に解明する。その結果得られた精緻な原因分析を活用し、課題解消に向けた大型の計画や戦略を緻密に構想していく。この王道的なプロセスを着実に辿るための指導を、岸本ゼミでは行っております。そして、そのプロセスの中で、大型の実務課題の解決に有用なノウハウや素養、思考法等を養っております。
ゼミでは2週に1度のペースで報告をしてもらい、それを基に私だけでなくゼミ生全員が参画する形で、議論をしています。テーマに関しては、私の専門分野と関係のないものも歓迎しております。他方、ゼミ生がインタビュー等を行う場合には、希望があれば、極力同行しています。ゼミ生の研究には、自分自身の研究のつもりで深くコミットし、熱くサポートする。これをモットーに運営をしております。
▼北林ゼミ
担当教授:北林 孝顕
北林ゼミでは、以下の3点を心がけて欲しいと思っています。第1に、グラデュエーションペーパー(以下、GPと呼ぶ)の作成では、実務における重要なテーマを選択してください。これまでの職務経験をベースに、多くの企業が共通して抱える重要な問題や既存の知識では解決が難しいような経営課題を洞察することによって、テーマ設定をして欲しいと思います。
第2に、問題の解決や優れたパフォーマンスをもたらすメカニズムをとことん考え抜いてください。問題の解決や優れたパフォーマンスをもたらすメカニズムに関する知識は、汎用性が高く、事業環境や業種が変わったからといって、すぐに陳腐化することはありません。GPでは、このメカニズムにこだわって欲しいと思います。
第3に、自らの主張を説得的に他者に伝達するための努力をしてください。論文とは、特定のテーマに関して、自らの主張を表明するものです。ただし、自分が経験的に知っていることを述べるだけでは、仮にその主張が正しいとしても、GPとしては不十分です。どうすれば自らの主張を説得的に伝えられるのか、この機会に考え抜いて欲しいと思います。
ゼミでは、原則2週に1度のペースで研究報告をしていただき、全員で討論を行います。論文の質は、それを書く人の能力や努力のみならず、作成過程における他者との討論やフィードバックの質によって決定されます。自身の研究に関心を持つだけでなく、ゼミの他のメンバーの研究もしっかりコミットして欲しいと思っています。
▼藏知ゼミ
担当教授:藏知 弘史
当ゼミでは、自らの問題意識とその問いをしっかりと育て、GP(グラデュエーションペーパー)にぶつけてスッキリする事を目指します。その過程では、「自分はどう変わるのか、会社や社会をどう変えるのか」、を自らに問い続けることに徹底的にこだわります。
研究を行う上では、大量の情報を正しくインプットする「物事を見る目」、知識と情報の相互・構造関係を把握、整理し、検討する「本質的思考力」、そして、発見した原理原則や仮説を説得的に分かりやすくアウトプットする「言語化能力」が重要になります。これらの能力は実務家であれば日々の業務、つまり、課題に対して仮説を立て、方向性を示し、具体案を提示して組織の意思決定を促すという活動にも大きく資すると思いますので、しっかりと体得出来るように運営しています。
ゼミではディスカッションを中心に据えています。問いとテーマを広く深く考え、仮説と実証プロセスを何度も繰り返しながら、みんなで本質的な原因を追究していきます。また必要に応じて、参考書籍の輪読や理論講義を行います。こうして、先述した3つの能力が備わっていく事になります。
▼諏訪園ゼミ
担当教授:諏訪園 貞明
先日、担当する講義「マクロ・ミクロエコノミクス」の資料を拡充すべく、経済学の入門書などを渉猟していた。その際、20 年程前に企画・立案を担当した新制度が成果を上げている旨の記載を、著名な経済学者の本に見つけた。経済法ほかの法学関係以外では初めてであった。昔から、「教科書に載る仕事」に憧れていただけに、感無量であった。他方、そうした新たな法制もあらゆる産業で機能していなかったら、「途半ばでしかない」と最近、改めて痛感していた。新しく開発された科学技術なども同じだろう。これまで当ゼミ生からは、新しい技術などをフル活用した健康経営プログラムや、業界初の流通制度の導入等の「画期的なビジネス・モデル実装」の提案などを受け、その度に脱帽の思いでいた。「独自性・新奇性」だけではない。第一に、法制上無理がなく、経済学的に腹落ちができる「ロジック」と、第二に、株主価値や従業員の生活などステークホルダーの利益を毀損しない、ロバストで持続可能な付加価値を生み出し得るかの慎重な見極め、「検証」も重要だ。様々な産業で機能するための十分条件だろう。
こうした点も教えられてきた気がする。VUCA の時代だと言われて久しくなった。そんな世の中を一新する「社会の形を創り変える仕事」を生み出すために、一緒に邁進していきましょう。
▼田村ゼミ
担当教授:田村 浩道
田村ゼミでは、主に以下の 3 つのポイントを運営方針としています。第一に、GP におけるテーマは徹底的に自分が解決したい問題にこだわる、という点です。GPの執筆においては、試行錯誤で研究方針に迷いが生じてしまうことも少なくありません。そのような困難な時にも、「自分の解決したい問題は何か」という原点を忘れないことが重要です。
第二は、ゼミのメンバー同士でお互いにリスペクトを持って議論するという点です。生成 AI の時代に相対的に価値が上がっているのは、「場を共有する仲間同士から生まれる新しい知恵」だと感じています。ゼミでは、ギブ&テークの精神を持って、お互いの研究について徹底的に議論を戦わせます。
第三は、定性情報のみならず、定量情報をシステマティックに取得して分析するという点です。幸いなことに、理科大 MOT にはブルームバーグ端末があります。これを利用して世界中の金融財務情報を必要に応じて取得し、研究に利用していきます。
私自身の研究の原体験は、若い時に派遣された UCLA での客員研究員生活でした。慣れない英語環境、プアな分析環境に大苦戦しながら、ファイナンスの査読論文を仕上げることができたことが、後の研究活動の自信にもつながりました。GP は、まさに新しい環境における今までの業務と異なる困難な研究活動です。皆さんとお互いにリスペクトしつつ、直面している技術経営の問題に対処していきたいと考えています。
▼中山ゼミ
担当教授:中山 裕香子
私が担当している科目「イノベーションを生むデザイン・デジタル戦略」や「デザインコンセプト創造」「先進ビジネスモデル」などに関するテーマはもちろんですが、私自身は前職のコンサルタント時代、主に放送局やネット系などメディア企業のコンサルティングに長年携わっており、メディア戦略や、広報・PR戦略、メディアを使ったマーケティングなどのテーマも歓迎します。とは言いましても、私のゼミで一番重視しているのは、皆さんの「好奇心」です。社会人になって尚、大学院で学ぼうという意欲のある皆さんは、好奇心の塊であろうと推察します。折角の2年間、これまでじっくりと考えてみたいと思っていたこと、実務とは直接関係ないのだけれど関心を持っていたこと、MOTに来て知った新しい分野などに取り組むのに良い機会だと思います。新しいことを知ること、深く探求すること、それをまとめることはとても楽しいことです。私のゼミで扱ってきたテーマはデザインやDXから、非認知能力開発のためのシステム構築、地域創生に寄与するポテトチップスの開発まで多種多様です。必要に応じて、専門家を招いての議論も行います。好奇心から発展した研究が多いですが、楽しいだけで終わるのではなく、ゼミ生の今後の実務家人生において、何事にも積極的に取り組むきっかけとなることを心掛けます。
▼日戸ゼミ
担当教授:日戸 浩之
ゼミの運営方針として、次にあげる 3 点を示しておきます。1 点目は担当教員(日戸)のカバーしている領域はマーケティングあるいは B2C 系の業界が中心ですが、コンサルタント時代の経験を踏まえて、できるだけ広くとりたいという想いがあります。ゼミで多様な議論を行いたいので、様々な専門性、問題意識、バックグラウンドの学生の方を歓迎します。(異才融合です)
2 つ目の点として、理科大 MOT のよき組織文化(自由に議論ができる場の形成など)をもとに、ゼミメンバーの学生と様々な情報収集や連携を図れる機会が充実するような運営を行う予定です。例えば担当教員が現在、科研費を取得して進めている組織活性化(従業員が生き生きと働く条件、イノベーションと組織との関係がテーマ)の研究などにも可能な範囲で協力を求めていきたいと考えています。
3 つ目に、時間のない社会人学生の皆様の事情も考慮して、体系的、効率的にゼミナールを運営していくという方針をあげます。そのために、グラデュエーションペーパー(GP)、レポートを作成する生産性を上げるノウハウを取り入れる予定です。私自身はコンサルタント時代には根性と気合いで何とかしてきました(若手メンバーと組んで論文執筆も多数、経験)が、ゼミでは先行研究の探索、仮説立案、データ分析などに関して、様々な方法論、ノウハウを共有しながら、個人および組織の知的生産性を上げていきたいと考えています。