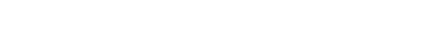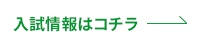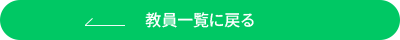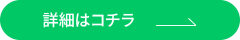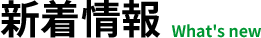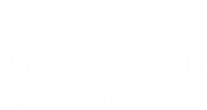能上 慎也 教授 Shinya Nogami
受講生の皆さんがなるべく
興味を持てるような内容を
分かりやすく説明するよう
心がけています。

1979年東北大学工学部卒。1981年同大学院工学研究科博士前期課程修了。1984年同大学院工学研究科博士課程後期課程電気及び通信工学専攻修了、工学博士。1984年4月より電電公社(1985年より日本電信電話株式会社(NTT)に改名)武蔵野研究所入社。以来、2006年3月までネットワーク設計・制御、情報・通信処理システムの性能評価などの研究に従事。2006年4月東京理科大学経営学部経営学科着任。以来、経営情報システム、オペレーションズリサーチ関連の研究に従事、現在に至る。
※嘱託教授
教員の志史
生まれは秋田県能代市(バスケットの強豪校である能代工業高校(現在は能代科学技術高等学校)がありご存じ方も多いと思います)という地方の小さな町で、小さいころから蛙や昆虫を取ったり、海水浴やスキーをしたりと外で活発に駆け回る子供だった様です。またスポーツ全般に興味があり、中学校では剣道部、高等学校では卓球部、大学では硬式テニス部、野球などを楽しみました。理科大に来てからは10年間ほど合気道部の顧問をしながら自らも合気道を学び、二段まで取得しました。これらから、何事にもまず興味を持って取り組んでみることの大切さを学んだように思います。
高校のころから、漠然とコンピュータやプログラミングに関係する方面の仕事に就きたいと考えており、大学の研究室はその方面の教授(専門が通信方式、伝送方式の先生)の研究室を選択しました。大学の卒業論文は、通信制御装置のインタフェースを作成する研究で、電子回路を設計しはんだごてで実際に基盤に部品を取り付けたりしました。大学院修士(博士前期)過程と博士(博士後期)過程では、オペレーションズリサーチ(OR)の中の一分野である「待ち行列理論(Queueing Theory)」を補助変数法という手法を用いて解析するという研究を行いました。これが私の中ではその後の研究生活の核となっています。
NTTの研究所に入ってからは、光LANの性能解析、ATMネットワークのトラフィック特性の解析、データフローコンピュータの解析、光ネットワークの性能評価、電話網における輻輳制御の研究、P2Pネットワークの解析などを行いました。
東京理科大学にきてからは、主に大学院生とともに待ち行列理論の解析、信号制御の解析、研究室配属問題、企業間提携のマッチング問題、入試情報の分析、ニューラルネットワークのアルゴリズム、経営情報の分析などの研究を行ってきています。
東京理科大学で担当してきた科目は、次の通りです。 【学部】情報通信ネットワーク、データ処理法、プログラミング論、基礎情報処理、経営データ解析、情報処理概論、ナレッジデータベース論、情報リテラシー、キャリアデザイン、オペレーションズリサーチ、情報システム、情報コミュニケーション、コミュニケーションネットワーク、企業体験演習、卒業研究、ゼミナール 【大学院】情報処理特論、大学院ゼミナール