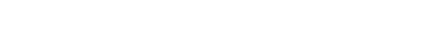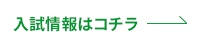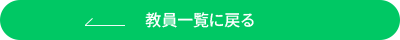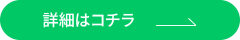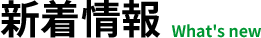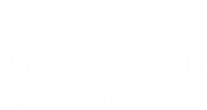藏知 弘史 教授 Hiroshi Kurachi
プリンシプル(原理原則)と
マネタイズ(経済的価値の創出)に徹底的にこだわる

1996年株式会社キーエンス入社、2002年よりPTCジャパン株式会社。2006年よりエンジニアリングIT企業のスタートアップに専務取締役兼COOとして参画。一貫してエンジニアリングソリューション領域を歩む。2011年に製品ライフサイクルマネジメント(PLM)とビルディングライフサイクルマネジメント(BLM)の両輪を事業基盤に据える株式会社アイスクウェアドを創業、代表取締役社長就任(現職)。
2017年東京理科大学大学院イノベーション研究科技術経営専攻課程修了、技術経営修士(専門職)。2023年より東京大学大学院工学系研究科建築学専攻共同研究員。2025年より現職。専門はアントレプレナーシップ、ベンチャーマネジメント。
※嘱託教授(みなし専任)
教員の志史
「必要な事は全てキーエンスで学んだ」
私は1996年に、23期生としてキーエンスに入社しました。当時は、創業者である滝崎さん(キーエンスでは全ての人をさん付けで呼びます)が社長を務められており、既に東証一部上場を果たしてはいましたが、まだまだベンチャースピリット溢れる会社でした。
滝崎さんは個性的なトップに依拠する経営には否定的で、とにかく仕組みと考え方にこだわっているところに凄さがあります。そして、「最小の資本と人で最大の経済効果(付加価値)を上げる」という経済原則を会社の経営理念の中心に据え、これを物事や人の評価軸とし、誰が考えても正しいこの原理原則に基づいて物事を判断し、これを徹底しています。
私はキーエンスでは7年間お世話になり、滝崎さんのビジネスに対する姿勢や考え方を徹底的に学ばせて頂きました。退職してもう20年以上になりますが、当時の同僚や先輩とも交流があり、未だに大好きな会社です。そこで、まずはこのキーエンスでの学びについて記したいと思います。
「何よりも大切なプリンシプル(原理原則)」
キーエンスでは「売上高は世の中への貢献の尺度である 」「付加価値とは粗利である 」「価値は顧客が決めること」「成長とは自らの価値を高めること」といった価値判断基準を示し、これこそがビジネスの原理原則であるとしています。そして「最小の資本と人で、最大の経済効果(付加価値)を上げる」、「目的・問題意識を持って主体的に行動する」、「市場原理・経済原則で考える」といった経営理念と行動指針を示し、これらの実践と徹底を全社員に求めます。
言葉の「意味合い」を理解させることを大切にしているのもキーエンスの特徴です。上記の価値判断基準は言い換えると、「売上高は社会へ受け入れられた度合いを示し、提供する製品の役立ち度の高さと粗利率は比例する。その価値判断基準は市場にある。そして、我々の成長なくして会社の永続はない。」となるでしょうか。特にミドルマネジメントに対しては、自分で常に腹落ちするまで意味合いを考えて言語化し、伝える力をつけることを重視しています。とにかくプリンシプルの徹底と浸透にこだわっているのです。
こうした、原理原則に基づいた判断や行動を徹底するというキーエンスでの原体験は、私が経営をする上で最も必要な迅速な判断力の源泉となっています。また、私自身の経験則よりも原理原則を重視するという考え方も、滝崎さんの経営理念や行動指針の影響を色濃く受けていると感じます。
「外資系企業への転職、そして起業家に」
そんな素晴らしい会社で楽しく働いていたのですが、若者によくある「自分の力を試したい」や、「外資系企業への憧れ」といった流行り病に侵され、外資系ソフトウェア企業に転職します。しかし、仕事は面白いのですが、マネジメントが気にくわないという状況に陥ります。結局、外資系企業で働いてみたいという好奇心から来る欲求は満たされたものの、私には外資系企業は肌に合わなかったのです。
外資系企業はもうこりごりだ。しかし、またキーエンスに戻るという選択は、心理的にも物理的にも相当ハードルが高い。そんな中、先に独立起業していた同僚の会社に経営参画するというチャンスを得て、起業家への道を進むことになります。
寝食も忘れて懸命に仕事に没頭し、マネタイズにも成功し、やっと会社を成長軌道に載せる事が出来た頃の事です。「経営方針の不一致」という、よくある話だが、非常に厄介な問題が発生してしまいます。結局、私が退任するという結果となり、私はまた新しい事業を起こす必要に迫られます。こうして、私は意図せずしてシリアルアントレプレナーの道を進むことになり、今日に至るまで起業家、経営者として活動しています。
「論理を求めて理科大MOTへ」
私も皆さんと同じように悩みを抱えていました。経験則だけではどうにも解決出来ない課題がある。正しい経営判断が出来ているか自信が持てない。結局、経営者としての地力が全く足りないのではないか。そんな悩みを私は経営理論に解を求め、理科大MOTの門を叩きました。
MOTではインプットとして経営理論を学ぶだけではなく、その概念や論理をつかって議論を深めていきます。特にゼミのディスカッションでは、「本質的思考力」と「物事を見る目」、そして「伝える力」が徹底的に鍛えられました。特に指導教官であった伊丹敬之先生には、経営者に必要な理だけではなく、心にまでご指導を頂き大変感謝しています。
こうしてMOTでの学びにより、自分自身の経営に対する解像度と会社の運営能力が上がっていくのを実感しました。論理を軸にした根拠のある戦略は社員に浸透しやすく、推進する上でも心に迷いがなくなる。期待はしていましたが、MOTでの学びをすぐに経営に活かすことは想像以上の効果となり、修了してからの5年間で会社は10倍を超える飛躍的な成長を遂げました。私が「理科大MOTでの学びは、成果に必ず直結する」と断言するのは、この強烈な成功体験に裏打ちされたものです。論理は絶対に裏切りません。
「学術と実務の架け橋に」
そして、2025年より母校である本学MOTで教鞭を執るという機会に恵まれることになりました。技術経営(MOT)は、「技術が持つ可能性を見極めて事業に結びつけ、経済的価値を創出(マネタイズ)するための学問」です。そして、起業成功の本質も同様に「マネタイズ」に成功するか否かです。
私の起業家としての経験と理科大MOTでの学びを基に、プリンシプルに基づいた理論構築とマネタイズにこだわった実務家教員らしい実践的な講義を通じて、互いに切磋琢磨しながら、皆さんの問題解決や成功に貢献したいと思います。