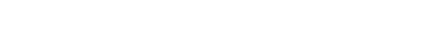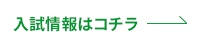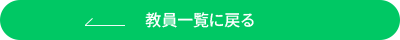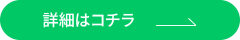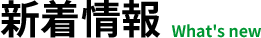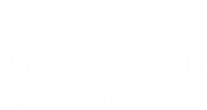岡田 将稔 教授 Masatoshi Okada
理論と実践の往復運動で
学びのエンジンを回すこと

1997年現三菱UFJ銀行入行。2021年よりWMコンサルティング部ファミリーオフィス室長(フェロー)。2024年MUFGファミリービジネス総合研究所長(兼職)。1997年立命館大学法学部卒業。2018年神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修了 博士(経営学)。2022年より神戸大学大学院経営学研究科客員教授。専門は管理会計、ファミリービジネス研究。
※嘱託教授(みなし専任)
教員の志史
【個人的な背景】
幼少の頃からファミリービジネスが身近にありました。祖父が創業した事業から父親がスピンアウトしたことで、外部環境の変化による栄枯盛衰を実感しましたし、ファミリービジネスの家系に生まれた影響もあり、自身の世代で何の事業に挑戦するのか?を考えるいわゆる「一世代一事業を興す」ことが使命感として備わっていたように思います。今後もライフワークとして取り組もうと考えている「ファミリービジネス研究」に対する研究動機はこのような個人的な背景が大きな要因になっています。
【なぜ社会人として大学院に進学したのか 】
社会人として数年が経過し本部勤務になった頃、「実務の中から日々溢れる情報に対して,どのように向き合えばよいのか?」と考えることが多くなりました。当時この問題意識を解消するにはビジネスに関する学問(経営学)を体系的に学ぶ必要があるのではないかと考えていました。ちょうどその頃,勤務先の国内大学院留学制度に合格して,仕事をしながら週末に経営大学院に通学することになりました。そして神戸大学MBAプログラム修了後には、もっと経営学について学びたいとの思いから、神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程(PhDコース:研究者養成)に進学をしました。結果としてMBAコースとPhDコースの合計6年間に亘り経営学を学ぶことになりました。
【理論と実践の往復運動で学びのエンジンを回す】
経営学を体系的に学ぶことの効用は,アカデミックの経営理論から現場での実践、現場での実践からアカデミックの経営理論へと往復運動を繰り返すことであると思います。そのため実務からエビデンスを獲得して研究する動機を持つことは,ごく自然な流れであったかもしれません。そうすることで理論と実践の往復運動が自分自身に浸透し,ビジネスや社会に貢献するための学びのエンジンを回し続けることが出来たと考えています。実務の中から日々溢れている情報の意味を理解して実践に活かしていくこと,そして共感できるアカデミックの経営理論と出逢うことで,実務上の悩みから救われることは,実務家が研究に携わる大きな価値であると感じています。
【“Big E Evidence”と“Little e evidence”】
カーネギーメロン大学のデニス・ルソーは,2つのevidenceについて識別しています。第一には,“Big E Evidence”と呼ばれる,科学的な手法に基づいて得られた因果関係に関する一般的な知識です。第二には,“Little e evidence”と呼ばれる,自社や組織特有に得られたエビデンスです。自身の研究は,“Big E Evidence”に対する貢献というよりは,“Little e evidence”と呼ばれる自社や組織特有に得られたエビデンスを明らかにすることでした。しかし,実務家として研究と実務の両方に取り組むことで,“Big E Evidence”も意識した“Little e evidence”の言語化や理論化に挑むことは重要な責務であったと考えています。
【参考文献】
Rousseau, D. M.(2006) Is There Such a Thing as “Evidence-Based Management”? Academy of Management Review 31(2): 256-269.
【実務家が研究に携わることで得られるもの 】
実務家が研究に携わることで得られるものとは,実務の中から日々溢れている情報を捨てることなく,情報そのものの意味を理解してアカデミックの経営理論をベースに一片の物語として紡いでいくことだと思います。そして得られた研究成果を再び実務に活かしていくことで、理論と実践の往復運動を繰り返すことにあると思っています。
【理科大MOTの皆さまへ】
実務に携わりながら大学院で学ばれることは理想的な環境だと思います。これからも是非一緒に理論と実践の往復運動で学びのエンジンを回していきましょう。