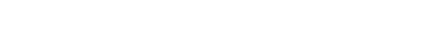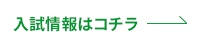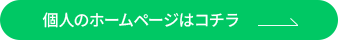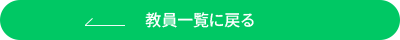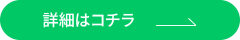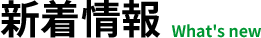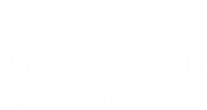内海 京久 教授 Kyohisa Uchiumi
理論と実務の
ギャップに着目し、
本質原因を鋭く探求!

東京大学工学部物理工学科卒業。本学大学院イノベーション研究科技術経営専攻専門職学位課程修了、同博士後期課程修了。博士(技術経営)。富士フイルム(株)にて、高機能フィルムの生産技術の研究開発に従事し、多岐にわたる新商品の開発や製造導入を経験。2024年4月より本専攻非常勤講師、産業能率大学非常勤講師。同年9月より高知工科大学経済・マネジメント学群教授。2025年4月より現職。専門は技術経営、イノベーション、経営史。著書に「イノベーション実現の条件」(共編著・文眞堂)。学術論文、学会発表、登録特許多数。
※嘱託教授(みなし専任)
教員の志史
「生い立ち」
物心つく前からクラシック音楽が大好きで、本当はヴァイオリニストになりたかった。5歳から習い始めたが練習が苦痛で、当然ながら「下手の横好き」。ソルフェージュの方が上手いので、先生に「歌手の方がいいのではないか」と嫌味を言われた。高校でオペラ部に入ったが、周りが上手すぎてすぐに退部した。しかし、今でも生まれ変わったらバイオリニストになりたいと思っている。
子供の頃はものづくりが大好きで、木工、鎧づくり、電子工作などに明け暮れ、手はナイフの切り傷だらけだった。中学でアマチュア無線技士を取ってからは毎週秋葉原でジャンク品を物色して、トランシーバーやアンテナをいろいろと工夫する日々で、夏休みに理科の電気分解用の安定化電源を教師から受注して製作・納入したりもした。
「オペラ歌手への道」
高校のオペラ部には、ヴァイオリンとしてはすぐに退部したのだが、テノールとして再入部した。音楽のテストで私の歌を聞いた部員にスカウトされたのだ。大学進学後オペラ熱が高まって、一時期イタリアオペラ歌手のプロを目指していた。しかし、憧れと実力とのギャップにかなり悩んだ末に、得意のものづくりを職業として、声楽は趣味で続けることとした。本場はイタリアであることによる文化・骨格の限界、自分がエンターテイメント気質というよりは職人気質であるといった資質の限界に気づいたこと、それらを考えるきっかけをいただいた恩人がいたことが決定打となった。
オペラを趣味と決めてから、不思議と舞台の話が増えた。オーケストラや歌手たちと舞台を作り上げる達成感と充実感、音楽演奏者としての感動と幸福感、レア・ユニークなのですぐに覚えてもらえる等、趣味としては贅沢なほど得られることが多く、今でも細々と続けている。
「ものづくりへの回帰」
会社では生産技術部に配属されて、ものづくり魂に火が灯った。人事部はよくぞ見抜いたという当たり配属であった。
アイデアがどんどん湧いてくるので、若さに任せて阿修羅の如く働いた。平日は業務、土日はオペラの2足の草鞋生活を満喫した。
詳細は省くが、時間を忘れて技術開発の日々を過ごし、実験計画、理論、データ分析、上司マネジメント、部下育成、関係部門巻き込み、産学連携などとことんやった。その結果、新商品・新技術の導入でいくつも成功事例を持つ、社内でも珍しい技術者になることができた。ところが、そのうちに2足の草鞋を脱がざるを得なくなった。それは、海外や国内の駐在業務によって顕在化した。舞台の話は一回断ると呼ばれなくなり、一回足が遠のくと再開しにくい。いや、それ以上にものづくりが面白くて仕方がなかったというのが大きい。そしてその頃から、漠然とした問題意識が芽生えてきた「なぜ新技術や新商品の開発を頑張っても事業が成功しないのか?どうすればよいのか?」
「経営学者への道」
上記の問題意識が芽生えて悶々としていた頃、上司からMOTを紹介してもらった。この恩は一生忘れない。そしてこれが人生を変えるきっかけになった。MOTに入学すると、そこで学ぶことや議論することが好きすぎて、時間を忘れて没頭した。この時に学んだ知識もさることながら、技術経営に関わる様々な現象の原因・メカニズムについての論理の作り方は、新商品・新技術開発の実務やマネジメントへ大いに役立った。一方で、MOTでの2年間を経て経営学研究に興味を持ち、博士課程へ進んで研究者としての素養を身につけた。心から尊敬できる師匠に遭遇できたことと、これを逃したら一生この機会はないと考えたことで、思い切って決断することができた。その後の10年間、実務と学術の二足の草鞋を履いた。高い相乗効果によって、実務での実績をあげながら、学術業績もあげることができた。しかし、それぞれが充実すると限界も見え始める。二刀流でのリソース不足を痛感し始めた。現状ではいずれも中途半端、しかし早く決断しないと手遅れになるという瀬戸際の状況の中、チャンスを待ち続けた。そこへトップジャーナルでの採択、非常勤講師や専任教員の話があったことで、転職を決断した。「好き」「やりたい」だけでは決断できない。それらに加えて「できる」という実績と実感を得て、さらに「外からの声」がかかってこそ、ようやく踏み出すことができた。
「学びの本質」
ふり返ってみると、2足の草鞋を履いては1足を選択(ピボット)する人生の繰り返しであった。草鞋の履き替えはいずれも大変重要な判断であったが、「好き」「得意」を大切にした上で、「できる」「外からの声」が決め手であった。また、脱いだ草鞋も人生の生きがいとして大事にしている。オペラ歌手・ものづくり・経営学者は、外から見ると一見飛び地に見える領域を渡り歩いて来たが、自分にとっては本質的に好きで得意ということが共通点であった。それが故に、いつでも新たな学びへの喜びに溢れて、尽きることのない好奇心に突き動かされてきた。好きで得意なことを探求すると、1つ知ると10知りたいことが増える。これこそが学びの本質であり、学び続けることのモチベーションであろう。
このMOTには、様々なバックグラウンドと想いを持った人達が集まっています。お互いの好きと得意を最大限に発揮することによって、深い学びと創造的な実践を一緒に実現し続けて参りましょう。