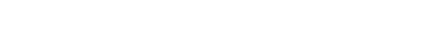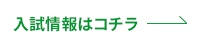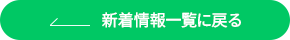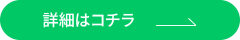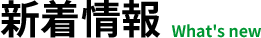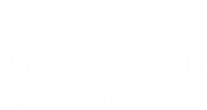2025.07.09 修了生が紹介するMOTの講義
専門科目「研究開発マネジメント」(内海京久教授)│第6回:資源動員の正当性 ~「理論と実務におけるギャップ認識」と「アクティブラーニング」~
2025年度春学期

内海京久先生がご担当の「研究開発マネジメント」を受講した。専門科目「研究開発マネジメント」の授業は、企業の研究開発マネジメントに関係する理論と実務における問題解決とのギャップを認識した上で、その解決策を導くための思考フレームワークや経験知を学ぶことを目的としている。第6回の授業「資源動員の正当性」は、研究開発における資源動員のジレンマに焦点を当て、市場・技術・競合の不確実性による資源動員の壁と創造的正当化プロセスにより壁を突破する理論を理解することを主な狙いとしている。
内海先生は、企業での実務経験が豊富で、またMOT修了生でもある。そのようなご経歴から授業には大きな特徴が二つあると感じられる。一つは「理論と実務におけるギャップ認識」であり、もう一つは「アクティブラーニング」である。
授業では、冒頭に理論の説明があり、その後、学生が事前に作成したレポートを⽤いて、各⾃の持つ問題意識を討議の形で共有する。今回のテーマである研究開発における資源動員のジレンマについては、市場・技術・競合の不確実性による資源動員の壁を取り上げるが、本内容は多くの企業で経験する課題である。自らの職場体験を語ることで次から次へと学生からの発言があり、議論が白熱する。こうした議論を基に創造的正当化プロセスによる壁の突破の理論を理解するのである。理論をベースに講義が展開される一般的な大学の授業とは異なり、各企業の学生が自社での課題を持ち寄り、議論されるため決して実務が置き去りにされないのである。設計された授業のプロセスを通じて、『理論と実務における問題解決とのギャップ認識』を明確にすることで、実務に貢献できる学びとなっているのだ。
また、授業の最後には、授業の振り返りの時間を設け、疑問点や示唆が得られた内容を纏めレポートとして提出する。後日、内海先生から全ての学生に返信、フィードバックがある。
ただ話し合ったり、発表したりするだけでは、「深い学び」とはならない。「深い学び」とするには、今回の授業のように学生と教員、学生同士が相互に議論して、脳にインプットされたものを脳でアウトプットするなど、思考や感情、記憶を基に学生が主体となって能動的に学習活動を行うことが重要となる。企業での経験(実務)を基に考え、理論を関連づけることで「深い学び」につなげていく活動は正に「アクティブラーニング」であると言えるのではないか。
2025年3月にMOTを修了し、授業から遠ざかっていたことにより、今回の授業を俯瞰した視点で受講することができたと感じられた。理論と実務におけるギャップを認識し、アクティブラーニングを通じて、実務に貢献できる示唆を得ることができる理科大MOTの授業は、大変貴重であると改めて気がついた講義であった。
執筆:2024年度修了生(製造業勤務)